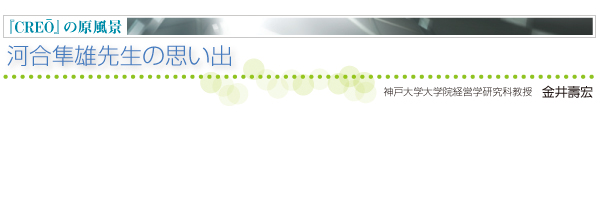河合隼雄先生の軌跡
私は、『河合隼雄―心理療法家の誕生』の書評(『エコノミスト』掲載)を執筆しました。それを援用しながら、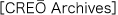 の「プロフィール」の補遺として、河合先生の足跡をたどってみたいと思います。
の「プロフィール」の補遺として、河合先生の足跡をたどってみたいと思います。
河合隼雄先生は、スケールの大きい学界人、多様な方々との対話・対談の達人、晩年は文化庁長官、趣味はフルートの演奏、自称「日本ウソツキクラブ会長」という多彩な顔をもちつつ、世界に向かって日本のあり方を発信されたユング派分析家にして箱庭療法の導入者でした。
丹波篠山の河合家。歯科医の父秀雄さんとテニスとバイオリンを弾く母静子さんの独立独歩の精神のもとで、男ばかりの兄弟のなかで育ちました。兄雅雄さん(自然人類学)、隼雄先生(臨床心理学)と弟逸雄さん(精神医学)は、兄弟でそろって京都大学の教授になります。とくに兄雅雄さんと先生は、人生でも知的に相互に刺激し合い、励まし合ったようです。
先生は、神戸工業専門学校を卒業して京都大学理学部数学科に進みますが、卒業後は数学者にはならず、奈良で数学の教師になりました。「高校一流の教師になるぞ」と決心したのですが、兄雅雄さんの勧めで大学院に籍を置き、心理学の世界に入ります。ここでも兄雅雄さんのアドバイスがあり、ロールシャッハテストに惹かれます。
UCLAのブルーノ・クロッパー(1900年―1971年。米国の心理学者)の論文を読んで、疑問に思う点を手紙に書いたのが契機となり、米国に留学します。
クロッパーに投影的技法を学ぶのですが、クロッパーのルーツにユング心理学があると見抜き、クロッパーも河合先生が米国の研究スタイルよりヨーロッパ的な知の探索が向いていると看破した。ユング研究所でユング派の資格を取るように薦めました。そこでいったん帰国し、1年後にチューリヒのユング研究所に入りました。
ユング研究所から生まれる資格取得者は、年に2、3人で、東洋人としては2人目の有資格者が先生でした。
彼の地での日々は、ユング心理学を深く知るという旅であると同時に、日本というものにどう向き合うかをスイスの地で探究する旅でもありました。
後年、母性社会日本の病理などを探究すると終始発言されました。そのルーツは、部分的には米国でのカルチャーショック、より大きくはユング研究所での自分が受ける分析、また自分が実施する分析の経験などにあります。そしてなによりも、日本神話を日本語以外で、深いレベルで語ることだったのです。