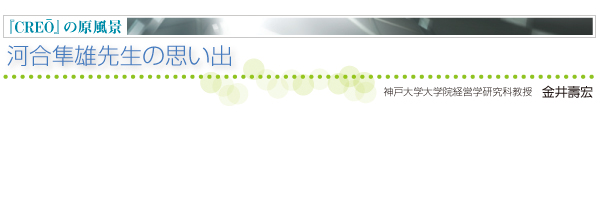河合隼雄先生との出会い ─ 金井壽宏の大学入試
私が京都大学教育学部を受験したのは、河合隼雄先生に学びたいと思ったことも大きな理由のひとつです。入試のとき、テレビで見て知っていた河合先生が試験監督をされていたので、歩み寄って、ぼくも臨床心理学を学びたいという話をして、ほんの短い時間に答えられないような質問をしたのです。
そのとき先生は「君が入学したら聞きにきなさい。いまは受験生の列に戻りなさい」と諭されたのですが、お人柄とそのお言葉に愛情を感じたものです。
それで、入学後聞きに行かなくてはと、先生の研究室の扉をノックしました。普通は勇気を奮ってノックするのでしょうが、入学したら聞きにきなさいといわれていたので、当然の権利のようにノックしました。
先生に、『ユング心理学入門』と『コンプレックス』は読みましたが、次にどの本を読むとよいですか、と質問しました。
考えてみれば、そのとき日本のユング派は河合先生お一人だし、先生の著作を読んでしまったら、ドイツ語か英語の本しかないのは決まっています。
河合先生はニコニコして、それはこれに決まっているとおっしゃって、ユング全集の中の第何巻かの、ブリンストン大学出版局から出ている英訳本, Two Essays on Analytical Psychology, を読むようにと、教えてくださった。
このとき先生が、学生を学部1年生から一人前の研究者として扱うところに、びっくりしました。普通であれば、あなたには無理ですが、こんな本があるからいつか読みなさいと言うだろう、と思います。
学生を学部1年のときから研究者として扱うということについては、川上真史さん(タワーズワトソン株式会社 コンサルタント)からも、京都大学教育学部に入学したときのことを聞いています。川上さんが入学したとき、河合先生が学部長挨拶で、「皆さん方が入学したこの1日目から1人前の研究者として接します」と話された。このことは一生忘れないことばになっていると聞きました。
臨床家を目指すほとんどの人は、修士課程に進みます。修士課程になると人数が絞られるので、河合先生が一人ひとりの名前を覚えてくださるが、学部のときは大勢いて覚えてもらえません。
やはり河合先生門下の倉光修教授(東京大学教育学研究科)から、河合先生が、倉光と金井の名前は学部のときから知っていた、といってくださったと聞き、これもまたたいへんうれしく思いました。