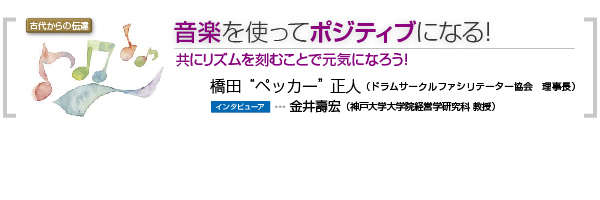リズム楽器との出会い
■ 金井 まず、ペッカーさんのリズム楽器との出会いについてお伺いします。どのように出会い、さらに踏み込まれたのでしょうか?■ ペッカー 幼稚園を経営していた実家にホールがあり、そこにはオルガンが30台とカホンという楽器のような大きな積み木が40個ぐらいありました。ホールでその積み木を放り投げると、カーンという音が響き、ホールエコーがします。そういう大音響設備のある中で育ちました。
小学生でドボルザークの「新世界」にハマりこみ、ホールいっぱいに大音響を響かせるという、普通の家庭ではあり得ない音の環境で育っていました。そして、高校ではシンフォニー・オーケストラ(交響楽団)に入り、打楽器を習いました。
■ 金井 クラシックからですね。
■ ペッカー そうです。ただ中学校のときはオンタイムでビートルズの洗礼を受けたので、バンドを結成しドラムセットを叩いていました。あまりうまくなかったのですが、叩くことが好きで、家から学校までスティックでタタツカ♪、タタツカ♪と道路やガードレールを叩きながら学校へ行くような変な子でした。
大学は東京に出て、ジャズ研究会に所属したり、ハワイアンズのクラブに行ってはコンガというラテンパーカッションを叩いているうちに、いつの間にかプロになっていたという感じです。
■ 金井 ご実家はどちらですか?
■ ペッカー 高知県の西部、四万十川のそばです。
冬になると山へみかんを採りに行ったり、秋には川で鮎、夏はうなぎを釣ったりと、もうとことん自然児ですね。
■ 金井 そういう環境だったので、ドボルザーグの「新世界」も普通よりも大きな音で聴けたのですね。
■ ペッカー 一般家庭では多分怒られるような大音響です。当時は、バーンスタイン作曲の『ウエスト・サイド・ストーリー』(1957年初演)も大好きで、クラシックと同じように大音響で聴いていました。
でもそれは、誰かに勧められたわけでも、こうしろと言われたことはなくて、自分で選択していった。
“先生”との出会い
■ 金井 1977年に海外に行かれる前に、リズムの世界で先生と呼べる方はいらっしゃいましたか?■ ペッカー その頃は、本気で誰かに教わろうとは思えなかった。当時はビデオもYouTubeもなく、レコードだけで、しかも日本ではラテンやマンボなどのブームが去った後の世代です。だから、これは本場に行くしかないとアメリカに渡りました。
まずロサンセルスに着き、サンタモニカビーチにセッションしている人がいると聞いて行きました。するとでっぷりと体格のいいおばちゃんたちがコンガ等でセッションをして、「コンガやりたかったらロスじゃなくてシスコに行きなさいよ」と言われ、その日のうちに飛行機でシスコに渡り、そこに住みつきました。
隣の部屋がプエルトリカンのパーカッション、下の階にはブラックアメリカンのパーカッション、左下の部屋にはシカゴから流れてきた年老いたブルースシンガーがいる、というような音楽長屋にいました。
そこで生活している人はキューバレストランで皿洗いをやっていたり、生活保障を受け、フードスタンプ(低所得者向け食料配給券)で生活していたり、すごく貧しかった。
でも朝になると、アフロアメリカンがアース・ウィンド・アンド・ファイヤー(アメリカのファンクミュージック・バンド)をドッカンと大音量でかけて先ず目が覚める、引き続きプエルトリカンのサルサがドカンときて、さらにはシカゴブルースというふうに、これがすごく楽しかった。
高校でクラシックをやっていたので、音楽教育はもちろん受けていますが、音符の読み方以前に、“音”とか“繋がる”ことの意味や心構えをその音楽長屋で教わったと思います。だから、言わばそこが“先生”です。
例えば、セッション中に自分の練習をしたり、自分のやりたいことをやろうとすると、「みんなが調和してやろうとするハーモニーの中で、お前は今練習しただろう」と指摘される。つまり、アンサンブルするときは、その調和が目的であって、一人一人がテクニックを磨く場ではないということをきびしく教わりました。