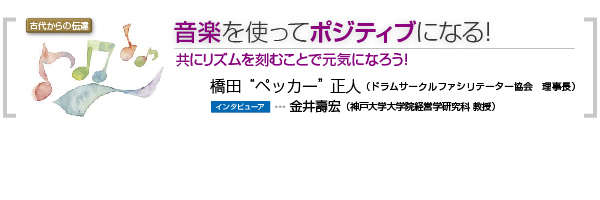“共”有する楽しさを、もっと子どもからお年寄りまで得るべき
■ 金井 シンセドラムの値段がどんどん安くなって、壁の端に置けるようなものまで売られるようになりました。一家のパパが子供に買って遊ばせたり、孫とおじいちゃんが取り合っている姿を想像したら、楽しいですね。しかも、健康増進にも、元気にもつながる。■ ペッカー そうですね。でも大事なことですが、一人で練習したり、納得するのではなく、グループでやる楽しさ、つまり“共”同ということを知ってほしいのです。
それがドラムサークルというイベントなんです。これは、輪になって即興音楽をやりながら、“共”同の楽しさや“共”感、“共”有する楽しさを、子供からお年寄りに得て頂くという、アプローチのひとつです。
そこでは、年齢や経験に関係なく、参加者に自由なコミュニケーションセッションをしてもらい、そこからファシリテーターがエンパワーメントを引き出します。そこはドラミングを習う場ではなく、ドラムやリズムを通してコミュニケーションを行うことが目的です。
その輪の中には人生が詰まっている。例えば、魚屋さんだった人がおじいちゃん、ピアノ教師だった人がおばあちゃんになってそこにいる。その老人の方たちの輪の中には、いろんな文化があるはずです。だから、「はい、これやって」という一方的なアプローチではなく、そこから出てくるものをファシリテーターが引き出したときに、その輪はすごく楽しいものになる。
■ 金井 どこの会社も人事部や人材教育部門に一人二人ぐらいリズム系でファシリテーターをできる人を育成できたら、だいぶ違ってきますよね。
■ ペッカー その通りですね。僕らを有料で呼ばないで、会社の中でドラムサークルファシリテーターがいれば、すごくいい世界になっていく。
■ 金井 トレーニング・ビート体験会は、ドラムサークルの一種ですか?
■ ペッカー ドラムサークルは自由な活動で、トレーニング・ビートはうまくなりたいとか、クライアントに即したカスタマイズできるようになるための活動。つまり、マップを描き、フレームが作れて、それに即したリズム運動でその企業のリズムを修正していく。トレーニング・ビートのトレーナーは、ドラムサークルのファシリテーターで、優秀な人でないとできない。
■ 金井 化粧の心理学で、元気がなくなっていた女性が、化粧をするだけで外に出て行くようになるといった例を見ても、ただきれいになる為だけでなく、自分らしくなるとか、元気に関わっている。化粧がどういう効果を持つのかを考えると、字面は「化ける」となっていますが、実際には「よりよく生きる」「元気になる」ことに関わっている。音楽やリズムも生きることと密着していたと気づくべきですね。