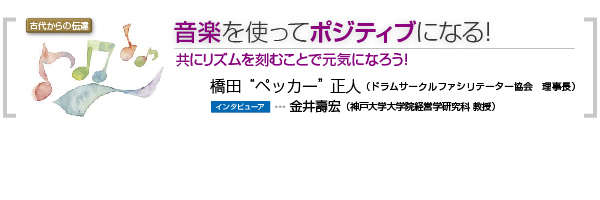古代からの伝達
■ 金井 例えばリズムを刻む、生きている、元気との関係で、苦痛を抱えている人が歌いだすと、周りがつられて誰かれともなく歌い出したり、映画の『スタンド・バイ・ミー』で子供は、死体を見てしまった後なので怖いはずなのだけど、家にみんなで帰るために、線路の道を歩きながら誰かが歌いだしたら元気になる。つまり、リズムが“繋ぐ”という役割だけでなく、音楽そのものが持っているパワーがありますよね。■ ペッカー 気分をマネジメントしているのです。ブルースは歌うことによって閉塞感を打破する力がある。綿花畑で朝から晩まで働かされて非常に疲れ、掘建て小屋のタコ部屋から霊歌が生まれて、それからジャズが生まれた。それは歴史が証明している“古代からの伝達”なのです。“音楽を使って精神的な気分を転換したり、プラスに持っていく”ことは“古代から僕らに伝達されたもの”なので、僕らはそれを次に伝える役割をしなければいけない。
■ 金井 “Five Long Years”というブルースの曲の歌詞で “Have you ever been mistreated? ” という繰り返しがあり、「ひでぇ目にあったことがあるかい?」と訳すべきフレーズが繰り返されます。すごい女性に会って、惨めになったときに、ありのまま惨めだと歌うから逆に元気になる。ブルースの歌詞を聴いていて元気になるのは、辛い時期に、カラ元気をつけるための元気づけをしているのではなく、その気持ちを素直に表現しているからこそ、逆に励まされますよね。しかも背後にレイジー(のろのろとした)で単調なリズムパターンが聞こえてくるので、一層元気になります。
■ ペッカー “共”有ですよね。同じ辛さを共有してプラスに変えていく。共有する程コーラスになるし、ゴスペルは手を叩いてリズムを自ら出して歌う。例えば、キリスト教だったら神がいますが、その向こうに僕は黒人のアフリカのよろずの神がいると思う。キューバは、キリストを信仰しているように見えていますが、じつはその向こうにはヨルバの神がいる。そういう信仰もあるのです。心の動きが信仰に結びつくのは当然の話で、どんな宗教を信仰するかということではなく、真なるものは一つで、その周りに音楽があり、数学があり、企業活動がある。すべて“心の動き”だと思いますね。
■ 金井 ある会社で研修のお手伝いをしていたとき、ヘルスリズムというプログラム(別名サクラ)を経験しました。REMO社(世界最大の打楽器メーカー)のりんごの形をしたシェーカーを持ち、7~8人ぐらいで輪を作って、隣の人に順に渡していく。シェーカーを渡すたびに鳴るシャッカ、シャッカという音にちょっとずつ揺らぎがあり、その音が揃っていないから、かえって心地がいい。
そこにファシリテーターが面白い装飾音を入れたりすると、さらに気持ちが入りますね。
■ ペッカー 僕もそれを使っています。企業で研修する場合は、電機会社だったら冷蔵庫やテレビが製造ラインに乗って上から下へ流れていきますよね。それは機械が責任持ってやっていますが、参加者にはその機械になってもらうつもりで、その会社の製品をシェーカーに置き換えています。
最初は目的を言わず、ただ順に隣に回してもらう。渡している間に「これって何かに見えませんか? 製造工程の製造ラインですよね」というところから、つぎにこれをちゃんと渡すためにどうしたら良いかをみんなで考えてもらう。一つのゲームを通して、心理学と組織論を使い、現実の職場に持ち帰って頂くことをやり始めています。
■ 金井 ある楽器メーカーの役員をされていた尊敬すべき知人和智正忠さんが、音楽が世に存在している意味をリズムという観点から知りたいと、役員を降りて東京医科歯科大学に博士課程で入学し、リズムを刻むことと免疫力で測定される健康との関係の研究で博士号を取りました。また、そのときデータ収集を手伝ってくれたのは、かつていた会社の人たちでした。私には、リズムと健康というテーマは、会社を超えて天下国家レベルの元気づけにも、こんな厳しいときほど生かしていってほしいと思います。
■ ペッカー そうなんですよ、国家がやるべきことなのです。でかい言い方ですが、自殺者が多すぎる。その原因の一番がうつ病です。病気になってしまったら医学の領域ですが、僕たちにも予防の手伝いはできます。輪になって、一緒にリズムを刻む、これはすごく大事なことです。それが、ヘルスリズムの目的です。