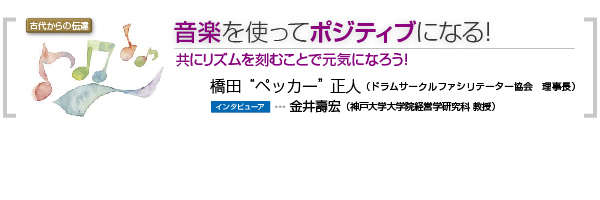パーカッションはリレーションシップの楽器
■ 金井 ポール・サイモンの曲で、スティーヴ・ガッドが叩いているリズムに初めて聞くなり何か違うと感じるものがあります。その根底にはモザンビークというキューバ発祥のリズムパターンがある。そのリズムによって、太鼓に奥深さを感じたり、ラテン系のリズムがバリエーションを広げると感じたり、レゲエと知らなくてもほとんどの人が聞いただけで違いが分かる。だから、バンドにラテンパーカッショニストがいれば、音がカラフルになったり、目立ちもする。その他方で縁の下の力持ち的な要素の両方があると思います。実際、プレイしていていかがですか?
■ ペッカー パーカッションは、「リレーションシップの楽器」だと思っています。ベースとドラム、リズムセクションとキーボードを結びつける、またはギターセクションを結びつける。必ずしも必要な存在ではありませんが、おっしゃったように音楽そのものが色彩豊かになり、バリエーションや多様性が出てくる楽器だと認識しています。
例えばコンガを叩くときに、さきほど先生がおっしゃったモザンビークというリズムがあります。これは1950年代末期に世界でツイストが流行り始め、キューバの青少年もダンスホールにツイストを踊りに行くようになった。するとカストロ議長はノーヤンキーの思想ですので、アメリカのリズムを自国の若者に踊らせないため、ページョ・エル・アフロカーンというバンドのリーダー、ページョというパーカショニストに、ツイストに勝るものをつくるよう命令をしてできたのが、このリズムでした。
■ 金井 リズムパターンとして、この人が発明した?
■ ペッカー 基本はナイジェリアのリズムですが、それをページョが新たに組み合わせ、発明した。そして、50年代末期にキューバ国民の若い人がみんな踊るようになった。要するに、プロパガンダなのですが、ツイストに流れなくてすんだことで、ページョはその後何年も功労者として国家の英雄となったという背景があるのです。88年にページョに招待をされて、キューバに行った際に、その功労表彰式に偶然、立ち会いました。
ただスティーヴ・ガッドはそういう政治的なものではなく、リズムの根源であるアフリカそのものを組み込んだ。だから、彼のドラムを聞いた人は、モザンビークというリズムから、アフリカを無意識に感じ、ハッとしたのだと思います。
■ 金井 他方で日本的なルーツについてお聞きします。例えば、デビッド・シルビアンというイギリスのロック・バンドの最新アルバム『マナフォン』が日本的だと言っている人がいます。間の取り方や、鼓の入り方やたくさんのパターンがどこか日本的です。囃子(はやし)とか、他ならぬ日本に生まれ育ったことで、私たちが自然とキャリーオーバーしているものがありますか?
■ ペッカー 偏っているかもしれませんが、私はすべてアフリカからでていると思います。アフリカ東部に大地溝帯(グレート・リフト・バレー)という南北に何千キロも横断する谷があって、そこから人類の起源が生まれています。ウエストアフリカにはマリンケ族や、中央アフリカには、ヨルバ族というナイジェリアの民族が占めていて、その人たちがアメリカに行ってジャズをつくり、キューバに行ってラテン、ブラジルでサンバをつくっている。
だから、僕はみんなが知っているリズムの起源は全部アフリカにあると思っています。例えば、ククという収穫を祝うリズムがあるのですが、これは(実際に叩く)。
■ 金井 元気になるリズムですね。
■ ペッカー これは僕らが慣れ親しんだ(実際に叩く)ツツタタツツタ♪という、お祭りのリズムがいつの間にかアメリカ経由で日本に入ってきて、それがエイトビートというロックに使われた。
だから、みんなと同じことをしていて面白くなく感じるならば、アフリカを見たほうがいい。アフリカのフレーズを自分のドラムに入れ込んだら、オリジナリティがあるし、気持ちがいいし、アピールもできる。なぜなら、それが本物だから。
それをスティーヴ・ガッドは知っていると思う。日本人がキューバのミュージシャンとセッションしているスティーヴ・ガッドを見て、そのまま真似るとそこで止まっちゃうわけです。スティーヴ・ガッドを通り越して、その先にあるアフリカという本質を見たときにスティーヴ・ガッドと同列に叩けるのです。
■ 金井 パーカッションの最大の使命である“結びつける”ということは、相当根源的な感じがしますね。
■ ペッカー はい。アフリカでは、人と人とが繋がることに太鼓が利用されている。音楽医療の分野において、アフリカでは太鼓のリズムで、自然免疫力のNK細胞(ナチュラル・キラー細胞)を活性化させていると言われている。彼らはそんなこと全く知りませんが、医学的にも病気が良くなるとか、予防のためにも使っている。その辺りについても、僕がアフリカに注目している点ですね。
■ 金井 民族音楽の繰り返しのリズムパターンでも、少しずつ揺らぎがあったり、ヒプノティック(催眠療法)といった治療的な感じがしますね。
あるいはドアーズ(アメリカのロックバンド)の長いオルガンソロは、催眠的な繰り返しがありますね。
■ ペッカー ドアーズの繰り返しもキューバから見るとマンボなんです。ティーティラ、ティーティラ、ティーティラというリズムがたくさんある。その回りが山あり谷ありで、マウンテンなのです。
僕は今日、須磨(神戸市)から車を飛ばしてきた。そこは山です。そしてそこから道が分からず高速道路にのってポートピアホテルで降りたら、行き先のホテルを間違っていたという意味で谷でした。そして、ようやくこの取材場所に着いた。これは僕の思ったとおりにいかなったという点で、良いリズムではありませんでした。ただこうやって今インタビューに答えられているのは、一日として見たら、良いリズムになっていくという見方をしているのです。