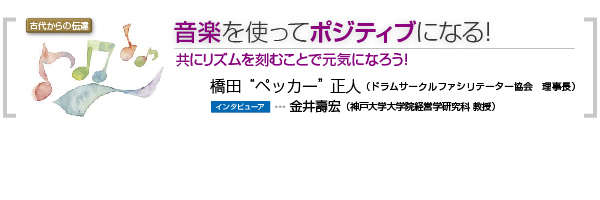世の中がすべて揺らぎでできている
■ 金井 「ハートビートを一つにする(Two hearts beat as one)」という言葉があります。二人で息があうとき、リズムも鼓動も合う。一緒にやっていることの楽しみや、生きていることの中に、“揺れ”や“揺らぎ”のようなことについて、お考えになることはありますか。■ ペッカー この世の中がすべて揺らぎでできている。偉そうに言えば、宇宙全部が揺らぎの途中で、まだ一拍目が終わっていないのです。ビッグバンで一拍目がスタートして、次のビッグバンで終わるまで、地球の一拍目も終わっていない。4拍子だとすると、4分の1もいっていないヨチヨチ歩きのこの世界で、完璧なものは一つとなく、揺らぎでできていて、全部が「我思う、故に我あり」というところにいくのです。それを考える自分の心の揺らぎが疑問を生じて、答えを見つける。答えが見えなくても、それでいいと思うところから余裕が生まれ、楽しいことが見えてくるのではないかと思います。
■ 金井 “ I think,therefore I am.” ── 「我思う、故に我あり」というデカルトのやや難しい言葉の英訳はかくも単純です。「私は考えている、だから存在しているのだ」。このthinkをsingに変えてみたい気がしますね。そして、IをWeにして。共に成し遂げることが生きることにおいても、仕事においても、一番の喜びです。「私は他の人とともにリズムを刻んでいる、だから生きている」となってほしいですね。
企業活動もリズム運動と認識する
■ 金井 こういう活動をなさってきて、ある時点から企業の世界、ビジネスの世界と繋がってきているので、ビジネス界に望むことはありますか。■ ペッカー 偉そうなことをいうと、企業活動もリズム運動だと認識したらいいのではないでしょうか。会社を興した人が1拍目を奏でて、時間が過ぎて軌道に乗り始めると、人手が足りなくなって、いいタイミングで経理の人を雇い、いいタイミングでマネジメントする人が入り、それで1小節ができたときに会社が整って2小節目に入る。
2小節目に入ると、例えば、もっとより良い研修の先生を雇ったり、いろんな会社と連帯を組んだりしながら、ドンドン広がりをみせ、大オーケストラになる。これは景気がいいという話です。
でもドカンと落ち込んだときに、どうやってそこから回復するかというと、業績が下がったからこれでもう駄目ではなくて、出だしはバイオリン1本の1拍目から始まった。だからこれでやり直すという回復のパワーに繋ぐよう、象徴的に物事を考えられるのではないでしょうか。
■ 金井 すべて音楽のイメージで、象徴的ですね。
■ ペッカー メタファー(隠喩)です。もちろん国も人間個人も、シンフォニーでできていて、ダイナミックスが、すごくフォルテシモもあれば、ピアニッシモのときもある。それを考えただけでもちょっと気分が変わりませんか。
そういう壁にぶちあたったとき、音楽や絵で心が洗われるというような、気分の変え方を音楽自体が持っているのです。
■ 金井 哲学者のニーチェの『悲劇の誕生』はより正確には、『音楽の精神からの悲劇の誕生』(“ Die Geburt der Trag?die aus dem Geiste der Musik ” 1872年)なのですが、このニーチェについて、伝記的資料を読むと、彼はイメージするもの全部を音楽で考えていたのではないかと思わせるところがあります。
■ ペッカー 直感的ですよね。企業で研修をやらせて頂いて思うことは、研修が進むほどに、みんなの顔がイキイキしてくる。実際に見たことはありませんが、滝に打たれたり、恐怖を我慢することでノルアドレナリンを刺激する研修があります。そのとき一瞬の集中力は生まれますが、それは長続きしない。僕はそれよりも幸せになるドーパミンを刺激してあげたほうが良いと思っている。
そのために音楽を使って、良いことをした人をみんなで褒めて、達成感を味わってもらいたい。それを味わった人はすごくズシッと入るんです。それは脳内伝達物質の動きという見方も、心の動きという見方もありますが、音楽だからと一言で片付けられるときもある。
■ 金井 ニーチェの悲劇の誕生が、音楽の精神からの悲劇の誕生だとしたら、また、別の観点では音楽の精神からの経営学の誕生なんていうのもあっていいのではないかと思え、いろんなバージョンがあり得ますね。
■ ペッカー それはもう“古代からの伝達”ですから。
■ 金井 レナード・バーンスタインが晩年に札幌芸術の森に来て、若手のオーケストラに指導したときのインタビューで、“ I never go to concert alone, I never go to movie alone. ” と言われました。要するに、「人と一緒じゃないとやらない」。“ Music is an essential part of my life. ” の後、“ People are an essential part of my life. ” ──「一緒に」が大切です。一人でやらないし、一人ではできないこともある、それも結構多い、というのはポイントですね。私が反省したのは、デジタルドラムでリズムが刻めて、周囲を気にせずに大きな音をヘッドフォンでも楽しめるようになった。でも、それだと共にリズムを皆で刻むというところがない点がよろしくないですね。
■ ペッカー トレーニングビートも最終的にはみんなで振り返りをやるのです。そうすると自分が気づかなかったことを仲間が言ってくれる、お互いが教えあうのです。僕も研修の講師も何も言わず、参加者が自分たちで気づいたことを言っているだけでも、気付きがどんどん深まる。それも仲間の意見だから、ものすごく長持ちする。