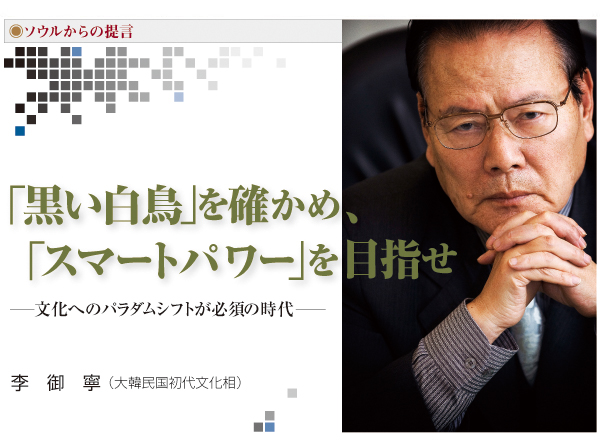● はじめに
昨年(2008年)9月15日、米国の大手証券会社リーマン・ブラザーズの破綻に端を発し、世界経済は「100年にいちどの大不況」の大波に呑み込まれた。あれから1年、各国政府や中央銀行はそれぞれ、「恐慌回避」の努力を重ねてきた。
米国の実質経済成長率は、年換算の前期比1.0%減と、1~3月期の6.4%減から改善された。
日本は二桁マイナス成長が続いていたが、3.7%増と5期ぶりにプラスになった。とはいえ、まだまだ危機からの脱出の出口は見えない。
この「大不況」は、1930年代産業社会が乗り切った、あの恐慌とはまったく体質が違う。あのときは、ニューディール政策とか、ナチスとの戦いとか、第二次世界大戦などによって、恐慌の不幸からなんとか立ち直り、戦後、新しい資本主義の時代に入っていった。
あの時代には、戦争でさまざまなものが破壊されたので、新しい需要を創出する道があった。つまり、生産過剰、オーバープロダクションを消化することができた。
21世紀の今日、特に重要なことは、情報知識社会といわれ、世界の人びとの懐の中までみなデータベース化され、世界のだれもが金の動きなどはすべてインターネットで捉えられている、と思い込んでいた点だ。ところが、情報知識社会で今回のような事態が発生したことは、知識そのものがなんの役に立っていない、ということを物語っている。
端的にいえば、金融経済問題だけではなく、政治・経済、社会、歴史までを包含した文化・文明そのものの問題だからである。
まず、二つの大きな視点から考えていこう。