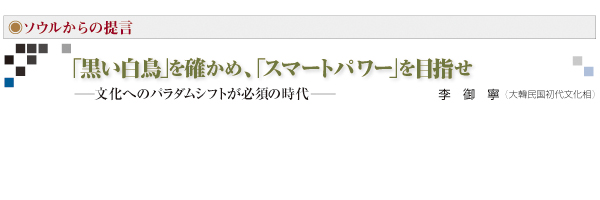●「軍事+経済パワー」から「文化パワー」へ
--第二の視点:文化パワーへの道
第二の視点は、文化パワーへの道を目指すことだ。これまで富国強兵によって軍事大国路線をとってきた国が、強兵を表に出さずに、富国を経済に置き換えてきた。大義のうえでは、軍事パワーを活かすための経済パワーであり、この二つを合わせてハードパワーになっていた。
アメリカの衰弱と後退は、富国強兵のパラダイムが効果を発揮することが難しくなったからだ。そこで現れたのが、ソフトパワーの文化とか人の心をコントロールする「文化パワー」の魅力である。
軍事力とは全然違い、経済力とも全然違う。外から抑える力ではなく、相手の心の中から湧いてくるパワーである。
その「文化パワー」によって、アメリカは、いろいろな大衆文化とか、さまざまな流行のマスメディアとか、インターネットのブログなどを通じて、ソフトパワーの力を発揮してきた。マイクロソフトの例からもわかるように、小さいもの、柔らかいものをつくり、大きくて硬いものを支配してきた。
●「言力」(ワードパワー)
そしてこのソフトパワーでいちばん重要なものは、「言力」(ワードパワー)、言葉の力である。これまで金が有り余っている人、権力がある人は、金と武力で抑えることができると考えていたから、言語の力にはあまり神経を使わなかった。しかし力もなく金もなく権力もないマイノリティーが、唯一たどりつくことができたのは、言葉の力であった。今まで世論など、ワードパワーを握り社会を動かしてきたのは、主流派ではなくマイノリティーであった。彼らはいつも社会を脅かしたり、支配したりしてきたが、チェック機能はあったけど、クリエイティビティは創出できなかった。
これからの世界では、言語の力、つまり、ソフトパワーを、軍人、政治家、経済人たちが知らなければならない。
だが、日本でも、韓国および中国でも、ワードパワーを理解している人はわずかしかいない。これまで権力、体力さえあれば、国をつくり、国民を支配することができると、考えられていたからだ。
これからは企業人も同じで、商品をつくるのに機能だけつくってもだめだ。人びとの心に触れるものをつくらないと売れない。これまでのように組織をととのえ、物質的な利益を生み出すだけではだめだ。
日本の小学校の先生や校長先生は、子どもたちに話すときに、権力を誇示してもだめだ。子どもたちの心に触れるように、その言葉自体を変えなければいけない。それがワードパワーの「言力」である。家庭内でお母さんとお父さんの話し方やその言葉も、同じである。
ところが、日本全体が言葉の世界に住んでいるのに、その言葉自体を空気みたいに取り入れているから、その貴重さが身にしみてわかっていない。
ここに膨大な武力をもったアメリカがいま苦戦する理由がある。武力でそこを支配したが、その国の人の文化のなかに深く入り、そこで相手の心を動かす、という装置、つまり、「文化の戦略」がなかったからだ。
そう考えると、日本の多文化主義にもプラスアルファする点が多々ある。たしかに滞在する外国人も多くなり、外国に行って外国人と一緒に物をつくる日本人も多くなっている。しかしこれまでは、お金の問題ばかりを考えてきた。言葉という戦略、つまり、言葉の生産性、クリエイティビティなどは二の次になっていたのではないか。
これからの時代には、「言力」がさまざまなメディアとかブログとかインターネットなどで、どんどん現れなければだめだ。
外交の問題にも文化を取り入れることが不可欠だ。軍事力と経済力を牽引していく強い文化が現れないとだめだ.。
これは家庭から地域から、学校から会社からすべて人と人のコミュニケーションの力から、それが文字であれ、インターネットのブログであれ、構わない。物を生産する以上にクリエイティブな力とコミュニケーション力を発揮し、ワードパワーをいかに盛り立てていくのかが、これからの試練になるだろう。