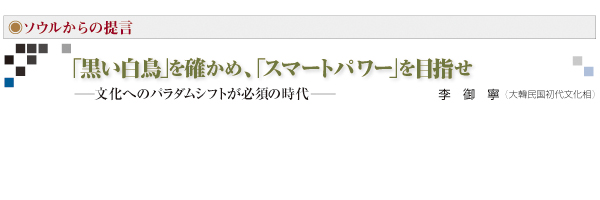● これからの生産性と仕事
これからの仕事は、「好む」「楽しむ」がカギになる。知識情報産業のキーワードは「好む」(like)だが、今後から労働自体を「好き」よりは「楽しむ」というパラダイムを変えないと、生産性も上がらず、労働システムも稼動するのが難しくなる。経済成長を上げないで生活の指数をあげるには、給料が半分になっても暮らしが楽しかったら、それこそ生産性を上げることと同じになる。
石器時代には、生産はものすごく低かったけど、二日に一度ぐらい労働したら暮らしていくことができた。No lack, No want で、欠けたものがなく、欲しいものがなければ、それでも充分だったからだ。
江戸時代の俳人たち、芭蕉などもみんな貧しくても、結構幸福だった。人間を楽しくさせるのは、お金ばかりではない。これまでは貧乏人の見栄っ張りの小奇麗な話の場合もあったが、これからはそうではない。
堪えしのいで節約して暮らすのではなく、給料が半分になっても楽しくやる措置はいろいろある。
共同体で趣味の集団をつくったり、一人一人が生きていく技を互いにシェアしたりしながら、昔の社会主義的の固い共同体ではなく、自分自身が喜んで参加できる時代になっている。文化とは相手とシェアしても失うものでなく、シェアすればそれだけ互いに楽しさを分け合うことができるものだからである。
(担当:三木敦雄)
(写真:筆者提供)
(写真:筆者提供)

イ・オリョン(李御寧・Lee O-Young)
1934年、韓国忠清南道に生まれる。ソウル大学、同大学院修士、文学博士。『韓国日報』、『朝鮮日報』論説委員。梨花女子大学教授、ソウル・オリンピック開閉会式を企画。韓国初代文化大臣を経て、現在、梨花女子大学名誉教授、『中央日報』社常任顧問。
著書は、韓国で個人著作集(30巻)のほか、小説、シナリオ、エッセイなど多数。
日本語の著書には、ベストセラーになった『「縮み」志向の日本人』(学生社版・講談社学術文庫版)、『韓国人の心[増補・恨の文化論]』、『蛙はなぜ古池に飛びこんだか』、『「ふろしき」で読む日韓文化』(以上、学生社)、『ジャンケン文明論』(新潮社)などがある。
著書は、韓国で個人著作集(30巻)のほか、小説、シナリオ、エッセイなど多数。
日本語の著書には、ベストセラーになった『「縮み」志向の日本人』(学生社版・講談社学術文庫版)、『韓国人の心[増補・恨の文化論]』、『蛙はなぜ古池に飛びこんだか』、『「ふろしき」で読む日韓文化』(以上、学生社)、『ジャンケン文明論』(新潮社)などがある。