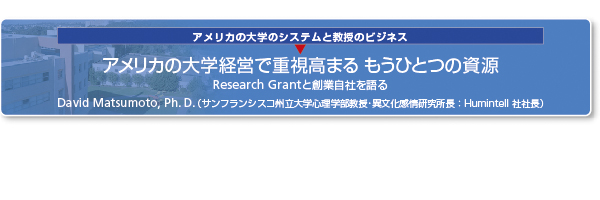● カリフォルニア大学デーヴィス校の例
■ マツモト先生 たとえば、カリフォルニア大学デーヴィス校(UC Davis)という大学があります。
── 農学が盛んで、スポーツチームの愛称が、Aggies になっているところですね。
■ マツモト先生 そうです。UC Davis では、student fee、州からの revenue、寄付金などよりも、research grant 関係の revenue がいちばん多い。農業関係の patent をたくさん抑えているからです。一例をあげれば、ナパ・ヴァレイには、ロバート・モンダヴィー・ワイナリーがあります。1966年創立時には、小規模の高品質のブティック・ワイナリーでしたが、現在では、650万ケースも生産する大きなワイナリーに成長しています。
── カリフォルニア州の農業関係は、全米No.1ですものね。
■ マツモト先生 大学で農業関係の新しいテクニックを生み出すと、さっそく農家に普及し、買ってもらえるわけです。そこでお金がまた大学に戻ってくる。UC Davis のいちばん大きな revenue source は patent なんです。
── そのパテントの契約を大学が抑え、たいていの大学は、知的財産(IP)の移転などにかかわる office ももっているのですね。
■ マツモト先生 そうです。とにかく研究がメインのアメリカの大学と企業との密接な関係は、農業だけでなくほかの業種でもほぼ同じです。UC バークレーとかスタンフォード、ハーバードとかイエール、そういう大学と、大手のエクセレント・カンパニー、たとえば、マイクロソフト、グーグル、ヒューレット・パッカードなどとの密接な協力関係は、おそらく日本では見られないのでないでしょうか。
── また、アメリカ政府自体も、grant や契約のプロセスを通して、アメリカの大学とその知的潜在能力をがっちり抑えていこうとしているわけですね。
■ マツモト先生 そうです。たとえば、NIH(国立衛生研究所)は、300億ドルも健康関連の研究の grant や契約に使い、心身の健康問題を解決しようとしています。── Grant と契約に巨額な資金を充てているわけですね。
■ マツモト先生 同じように、国防省も億ドルまでいきませんが、何百万ドルも grant と契約にあてて、大学との関係をがっちり抑えています。このように、アメリカ政府は合衆国と世界最高の知的財産を引出し、大学との強い絆を築こうとしているわけです。日本ではそうしたパートナーシップの関係をつくるのは難しいと思いますが。
これまでアメリカの大学側だけに立って話してきましたが、現実には、国によって知的財産の管理整備の度合いなどが違い、いろいろ問題があります。
── たとえば?
■ マツモト先生 いま、日本のある大学の研究者と交渉しています。研究成果の IP の所有権や交渉窓口がどうなっているのか、はっきりしていないのです。大学なのか、先生個人なのか? こちらはクリアなので、そちらもクリアにしてほしいといっても、わけがわからない。大学の弁護士も連れてきたんだけれども、駄目だった。
日本の大学はもう少し気をつかう必要があると思いますよ。
── 日本の大学の IP については整備度にはまだ問題があるんですね。大学によっても違いがあるでしょうし、研究対象すべてにわたって、IP についての意識が行き届いていないかもしれません。
日本では、マツモト先生のような社会心理学の分野での IP の商品化は、まだ珍しいのではないでしょうか。
■ マツモト先生 少なくとも、日米の大学がパテントなどの交渉をスムーズに行え、conflict になったり、international law で訴えたり訴えられたりすることにならないようにしなければいけませんね。日本では、マツモト先生のような社会心理学の分野での IP の商品化は、まだ珍しいのではないでしょうか。
── さて、マツモト先生の創業された会社とその業務について、具体的なお話を伺いたいと思います。