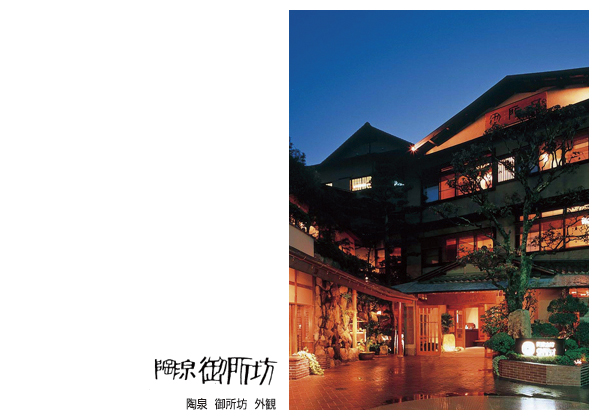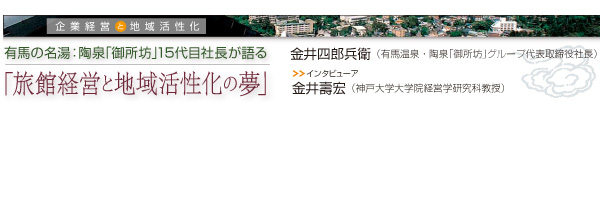●「若者の来る町にしたい」という思い
■ 金井社長 十和田市のビジネス旅館の駐車場の近くで、洒落たピザハウスを見つけたのです。当時の札幌には、東京のコピーはあっても、神戸を真似ることはありませんでした。
ところが、その店先に立てた道標に、神戸まで何キロとあるではありませんか。
それを見て、神戸のトアロードのNHK前に「ピノキオ」というピザ屋があり、そこにも道標があったことを思い出しました。十和田のピザ店のご主人は、神戸で修業した方だったのです。
このご主人は、都会に出て何かをしようというのではなく、都会の人を田舎に呼びこんでいたのです。週末には三沢あたりから若い女性がやってきて、平日にはもんぺをはいた近所のご婦人がピザを買いにくるという、田舎でしかできない店をやっていました。
それまで私は、外国に行きたいとか、外にばかり目を向けていました。この出会いで、視線が変わりました。有馬に来るのはお年寄りが多いのですが、有馬にも若い人を呼びよせ、自分たちも住みたい町にできるのではないか、という思いになりました。
■ 金井教授 有馬の町に若い人を集客する仕組みを考えるきっかけになった、大事な出会いだったのですね。お年寄りばかりの温泉街ではなくて、やりようで若い人も来てくれる。そういう思いを抱いて神戸に戻ってこられた。
●「有馬は神戸観光のお荷物」 ─ 「有馬を何とかしなければいかん」
■ 金井社長 有馬に帰ってきてしばらくは遊んでいました。ラジコン飛行機をつくって、毎日のように空き地で飛ばしていました。いま考えると、それも、ものを考えたりつくったりする重要なプロセスだったと思っています。1981年神戸で開催されたミニ博覧会「ポートピア81」のころのことです。神戸市の観光白書に「有馬は神戸観光のお荷物」と書かれました。そこで、大学を出て他所で修業して有馬に戻ってきていた、同世代の若者の何人かと「有馬を何とかしなければいけない」ということになりました。
毎週水曜日にお煎餅屋さんの2階に集まって、ああでもないこうでもないと話し合いました。
そのころ創刊された『るるぶ』の編集部に、有馬温泉を取り上げてもらおうと働きかけました。ところが、「有馬温泉に何があるの」という反応が返ってきました。そこで奮起して、何もないなら、自分たち若者が何かをつくろうと、イベントを企画しました。