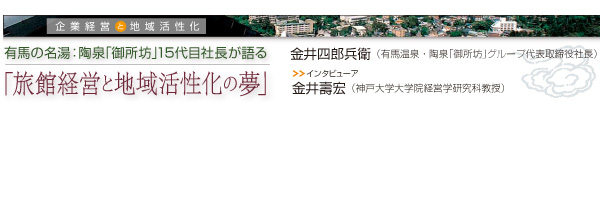● 本丸 「御所坊」などの旅館経営と改築
─ 無法庵・綿貫宏介先生との巡り合い
■ 金井教授 こんどは、本丸の旅館についてお伺いします。「御所坊」という伝統を踏まえて、「花小宿」、「花卿里」、「アブリーゴ」、「御所別墅」という宿をつくり、旅館としての絶えざるイノベーションをされていますね。■ 金井社長 「御所坊」は、木造を生かしました。そもそもは、鉄筋改良よりも木造をリニューアルしたほうが安くつくという発想でした。また、商業施設で木造の3階建ては新たにつくれないので、古くなっても価値が残るだろうとも考えました。
私は、ものを考えるときにメリットとデメリットを箇条書きにして検討します。「御所坊」は、木造のメリットが多いと思ったから、そうしたのです。
どのようにリニューアルしたらいいか。その、ストーリーをつくるとき、「御所坊」が一番輝いていた時代はいつなのだろう、と考えたのです。
それで、谷崎潤一郎が泊まった昭和の初期のことに思い至りました。谷崎の倚松庵は、日本と中国と英国が入り混じったような、いわば上海で見られるような感じがします。また、若いころにいた神戸外国人クラブの雰囲気も同じようでしたので、「御所坊」に取り入れやすいと思ったのです。
前年につくったカフェ・ド・ボウがレトロな雰囲気でヒットしていましたので、迷うことなく、レトロをデザイン的なコンセプトとして決めました。
さらに広間をなくしてしまうことによって、一つ一つの客室が大きくできるとか、一人のサービス係が三つの役割を果たすには、どうするか、「御所坊」の総合リニューアル・プランを考えました。こうして自分でプランを考えてから設計士に依頼しました。
しかし、人から、「御所坊」は伝統があって風格があるけれど、もうひとつ、ブランド戦略を加えないとダメだ、と指摘されました。ひらめいたのが、「イギリスの宝探しゲームのような絵本を参考に、漢詩で物語をつくろう」ということでした。
それで、人を通して、神戸在住の無法庵・綿貫宏介先生と巡り会いました。綿貫先生とニューヨークに出かけて、昔のフォーシーズンのように、古い建物を生かす世界的な風潮が起こっていることを目の当たりにして、現在の「御所坊」が誕生したのが、1987年です。
その当時は、規模で競うのではなく、縮小してもクオリティを高めるというのが、世界の超一流ホテルの傾向でした。「御所坊」もその流れに沿っていました。